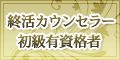相続に関わる法改正

・配偶者への居住用不動産贈与等(2019.7.1施行)
配偶者に自宅を遺す方法は、相続や遺言だけではありません。贈与することで、配偶者に確実に自宅を遺してあげることができます。
今回の法改正では、自宅の生前贈与、遺贈が配偶者にとって有利になります。これまでは自宅を贈与すると相続財産の前渡しであるとして、相続時には受け取る財産が少なくなることがありました。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産を配偶者に遺贈(遺言書)または生前贈与した時は、その土地と建物は特別受益の持ち戻しを免除します。(相続財産に加算しなくてよい)
配偶者は自宅を確保しつつ、預貯金などの取り分を減らさないことになり、老後の生活の安定につながります。
生前贈与のデメリットとしては、登記代(登録免許税20/1000)が高くなります。
1000万円で20万円の登記代がかかります。かつ、不動産取得税(評価の3/1000)がかかります。1000万円で3万円の取得税がかかります。
遺贈の場合は、相続と同じ登記代(登録免許税4/1000)は1000万円で4万円となり、不動産取得税はかかりません。
・特別の寄与(2019.7.1施行)
これまでは、たとえば長男の嫁が義父母の介護に努めたとしても、嫁は相続人ではないため、遺産はもらえませんでした。(遺言書に遺贈すると書いておけば遺産をもらえますが)
今度の改正では、その長男の嫁が相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
いくら請求するのか、当事者間で話し合いができればいいのですが、現実を考えると難しいですよね。
算定するには第三者の日当額×療養看護日数×裁量割合で考え、計算することになります。
たとえば、被相続人を2年間、1日合計1時間、介護をしていた場合
相続人は3人
約6000円×365日×2年×0.7(裁量割合)=約300万円
裁量割合というのは、有資格の介助者のサービスについて、介護事業所に対して支払うべきものを考慮し、減額した割合です。
各相続人は相続分が3分の1ずつだと、それぞれ100万円の支払い責任を負います。
・預貯金の取り扱い(2019.7.1施行)
被相続人の銀行口座は亡くなったことを銀行に知らせると、口座が凍結されて遺産分割協議がまとまるまでお金が下せなくなるのが原則です。ただし、当面の生活費や葬儀費用のため、100万円前後の払い戻しができる金融機関もあり、任意の扱いがされていました。
今回、一定金額までは相続人は単独で払い戻しができるようになりました。
相続開始時の口座残高×法定相続分×1/3
1金融機関につき150万円が上限です。
たとえば残高900万円の口座から配偶者が払い戻す場合
900万円×1/2×1/3=150万円
ただし、必要書類を持参しないと手続きはできません。
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書
・遺言執行者の権限の明確化(2019.7.1施行)
たとえば遺言書で愛人にマンションを遺贈すると書いていた場合、遺言執行者を指定していないと相続人全員の実印を押してもらわないと登記ができませんが、遺言執行者を愛人に指定した遺言書を作っておくと相続人の印鑑証明書は必要ありません。
私は公正証書遺言を作成する依頼をいただいた場合、必ず遺言執行者を決めて遺言書に書いておきます。自筆証書遺言のご相談をいただいたときも遺言執行者を指定しておくようお話します。
遺言書の中で、遺言執行者を指定しておくと遺言執行者はその遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言執行者がその権限内においてして行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます。
相続人が勝手に遺産を処分(分割、名義変更など)することは原則としてできません。
今回の改正前には、遺言執行者は相続人の代理人とみなすとあり、トラブルの原因となっていました。
また、指定されていた遺言執行者が入院や事情により遺言の内容を実現できない場合は、復任権により第三者に代わりに執行をしてもらうことができます。
遺言執行者には未成年者や破産者以外なら誰でも指定するこはできます。弁護士や行政書士などの専門家を指定することも可能です。
遺言執行者は断ることもできますが、就任した場合
自分が就任したこと、財産目録、遺言書の写し、相続関係説明図を相続人全員に送付します。
遺言書と遺言執行者の印鑑証明書、実印、戸籍謄本一式を用意し、金融機関での解約手続きなど遺言書の内容を実現します。
そしてすべて終わった時点で遺言執行終了通知を相続人全員に送付します。
私も数年前に遺言執行者として手続きを行いましたが、相続人の中には遺産をもらえない相続人にも遺言書の写しや財産目録など送付しないといけないので、送付したところ相続人として1円も自分は相続できないことに納得がいかないと言われたことがありました。
このケースは、兄弟相続だったので、遺留分もないので丁寧に説明をしました。
・遺留分侵害額請求権制度に関する見直し(2019.7.1施行)
遺留分とは、最低限保証されている相続分のことです。
これまでは、不動産等が遺留分減殺請求の対象になると、その不動産そのものの一部を取得するのが原則でした(共有状態となる)
今回の改正で、遺留分に相当する金銭で支払ってもらえるようになりました。
遺留分を計算するときの対象財産となる生前贈与(特別受益)は、相続開始前の10年間となりました。
・相続の効力に関する見直し(2019.7.1施行)
今では遺言書等により相続した不動産が法定相続分を超えていても登記をしなくても有効でしたが、改正で法定相続分を超える部分は早く登記をしておかないとこれは私の不動産ですと第三者に主張できなくなりました。
・配偶者居住権の新設(2020.4.1施行)
配偶者居住権というのは、配偶者が亡くなるまで居住用不動産に住み続けられる権利です。自宅を所有権と居住権に分けることで、自宅以外の遺産を取得しやすくなるメリットがあります。
具体例として、夫が亡くなり自宅の評価額3000万円、預貯金2000万円 合計5000万円
相続人は妻、息子1人 法定相続で分けると2500万円ずつとなります。
事例1 法定相続で分けると、母は自宅を相続し、息子は預金2000万円と母から500万円を息子に渡すことになります。→母は預貯金は相続できずこれからの生活費の不安があります。
事例2 自宅の所有権は息子にし、居住権を母にします。母の平均余命から配偶者居住権を1500万円、負担付所有権を1500万円とし、預金は1000万円ずつ分けることになります。
→母は自宅に住む権利とこれからの生活費として1000万円を相続することができました。
遺贈による場合は、その配偶者居住権を相続財産に加算しません。
遺産分割による場合は、配偶者居住権も相続財産の対象となります。
・法務局における遺言書の保管等に関する法律について(2020.7.1施行)
自筆証書遺言は遺言者の住所地等を管轄する法務局で預かってもらえる制度ができました。改ざんや隠ぺいや紛失のリスクがなくなるのはメリットです。
法務局が保管するので、検認手続きは不要となります。
遺言者の死亡後に、相続人等は遺言書情報証明書の交付請求、閲覧をすることができます。
保管の申請に必要なもの
自筆証書遺言
申請書
添付書類(本籍の記載のある住民票等)
本人確認書類(マイナンバー、運転免許証等)
手数料(収入印紙3900円)
・相続開始後に共同相続人が遺産を使い込みをしたときに関する制度(2019.7.1施行)
これまでは、一部の相続人が遺産を遺産分割協議の前に使い込んだ場合、使い込んだ分は遺産ではない(遺産分割の対象にならない)ことになっていたので、不公平でした。
改正により、使い込んだ相続人を除く全相続人の同意があれば、使い込んだ財産を遺産に組み戻すことができます。使い込んだ遺産はすでにもらった財産として計算でき、公平な遺産分割が可能になりました。